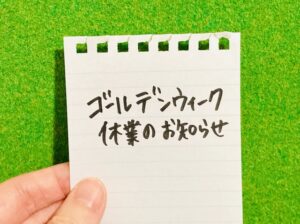【知って得する】隣の木の枝が越境!民法改正で変わったトラブル対処法とは?
隣地から伸びてきた木の枝に悩まされた経験はありませんか? 日照が遮られたり、落ち葉の掃除に困ったり、時には建物に被害が出たりと、さまざまなトラブルに発展しがちです。
これまで、越境した木の枝の問題は「隣の木だから」と諦めたり、解決に多大な労力を要したりすることが少なくありませんでした。しかし、令和5年4月1日(2023年4月1日)に施行された民法改正によって、その対処法が大きく変わったのをご存じでしょうか?
この記事では、民法改正前後の越境した木の枝に関するルールの違いを詳しく解説し、トラブル解決に向けた具体的なステップと注意点をお伝えします。
民法改正前:なぜ解決が難しかったのか?
民法改正前は、隣の木の枝が越境してきたとしても、原則として越境された側が勝手にその枝を切り取ることはできませんでした。民法第233条には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定められていたためです。
この規定は、木の所有者の財産権を保護する一方で、越境された土地の所有者にとっては大きな負担となっていました。木の所有者に枝の切除を依頼しても応じてもらえない場合、最終的には訴訟を提起し、判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。これには時間も費用もかかり、隣人との関係悪化も避けられず、泣き寝入りするケースも少なくありませんでした。
特に困難だったのは、以下のような場合でした:
- 木の所有者が不明な場合
- 木の所有者と連絡が取れない場合
- 竹木が複数人の共有で、共有者全員の同意が必要な場合
一方で、越境してきた木の「根」については、改正前から越境された側が自ら切り取ることができました。枝と根で異なる扱いがされていた点も、混乱を招く一因でした。
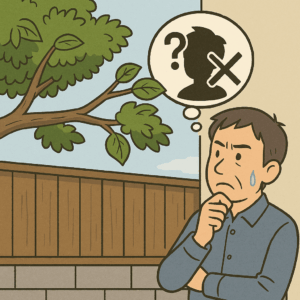
民法改正後:何が変わったのか?
令和5年4月1日の民法改正により、越境した木の枝に関するルールは、越境された土地の所有者にとって、より迅速かつ円滑な解決が可能となるように見直されました。
主な改正ポイントは以下の4点です。
1. 自力で枝を切除できるようになる条件の明確化
改正後の民法第233条第3項では、以下のいずれかの条件を満たせば、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるようになりました。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内(目安として2週間程度)に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき(例:倒木の危険があり、人や建物に被害が及ぶ可能性がある場合など)
これにより、これまでは訴訟を起こさなければ自力で解決できなかった問題が、一定の条件のもとで可能になったため、トラブル解決へのハードルが大きく下がりました。
2. 共有地の場合の新ルール
竹木が数人の共有に属する場合、各共有者が単独で枝を切り取ることができるようになりました(民法第233条第2項)。これにより、一部の共有者が所在不明でも、判明している共有者に対応を求めることで解決が可能になりました。
ただし重要な注意点として、催告を行う場合は共有者全員に対して催告する必要があります。一部の共有者が所在不明の場合、その不明者に対しては催告は不要ですが、判明している共有者全員には必ず催告しなければなりません。
3. 切除費用の請求が可能
自力で越境した枝を切り取った場合、その切除にかかった費用を木の所有者に請求できると考えられています(民法第703条、第709条)。枝が越境して土地所有権を侵害していることや、本来の義務を免れることを踏まえ、基本的には竹木の所有者に請求できるとされています。
費用を請求する際は、複数社から見積もりを取り、客観的な金額を提示できるように準備しておくと良いでしょう。
4. 隣地使用権の拡充
越境した枝を切り取るために、必要な範囲で隣地に立ち入ることが可能になりました(民法第209条)。ただし、これはあくまで「必要な範囲」であり、隣地所有者への事前通知や、損害が最も少ない日時・場所・方法を選ぶといった配慮が求められます。
越境した木の枝トラブル、どう対処する?
民法改正後の具体的な対処ステップをご紹介します。
1. まずは隣人との話し合い
最も大切なのは、いきなり枝を切るのではなく、まずは隣地の所有者と直接話し合うことです。越境している状況を伝え、枝の切除をお願いしましょう。相手に事情を理解してもらい、合意の上で解決できるのが理想です。
2. 催告書の送付
話し合いで解決しない場合や、相手が切除に応じてくれない場合は、「相当の期間内に切除しない場合は、ご自身で切除する」旨の催告書を内容証明郵便で送付します。
重要な注意点:
- 竹木が共有地の場合は、判明している共有者全員に催告する必要があります
- 一部の共有者が所在不明の場合、その者に対しては催告不要ですが、判明している全員への催告は必須です
- 相続未登記で相続人が複数いる場合は、大変な作業になることもあります
3. 専門業者への相談・依頼
催告後も動きがない場合や、木の所有者と連絡が取れない場合、あるいは急迫の事情がある場合は、ご自身で枝の切除を検討することになります。しかし、高所での作業や、電線に近い場所での作業は危険が伴います。また、適切な剪定方法を知らずに切ってしまうと、かえって木を傷めてしまうこともあります。
安全かつ確実に作業を行うためには、私たちのような専門の伐採業者や造園業者に相談・依頼することを強くお勧めします。専門知識と技術を持ったプロであれば、安全対策を徹底し、適切な方法で作業を行います。また、近隣への配慮(作業前の挨拶、養生、作業後の清掃など)も怠りません。
4. 費用請求の検討
ご自身で枝を切除した場合は、かかった費用を木の所有者に請求できると考えられています。請求する際は、作業内容と費用を明記した請求書を作成し、可能であれば複数の見積もりを比較検討した上で、客観的な金額を提示しましょう。
トラブル予防と円滑な解決のために
越境した木の枝のトラブルは、当事者間の関係を悪化させるデリケートな問題です。
定期的な手入れの重要性
自身の敷地の木であっても、定期的に剪定し、隣地への越境を防ぐことが何よりも重要です。これまで以上に、木の所有者は適切な管理が求められるようになっています。
日頃からのコミュニケーション
隣人との良好な関係を築いておくことで、いざという時の話し合いがスムーズに進みます。
早めの相談
問題が大きくなる前に、自治体の無料法律相談や弁護士、司法書士などの専門家、あるいは地域の信頼できる伐採業者などに相談することも有効です。必要以上に枝を切りすぎたり、隣地所有者との思わぬトラブルを避けるためにも、専門家への事前相談をお勧めします。
まとめ
民法改正により、越境した木の枝のトラブルは解決しやすくなりました。しかし、だからといって安易に自力で解決しようとせず、まずは対話、そして必要に応じて専門家の力を借りることで、安全かつ円満な解決を目指しましょう。
改正民法では「竹木の所有者に枝を切除させる」という原則は維持されており、自力切除はあくまで例外的な措置です。良好な近隣関係を保ちながら、適切な手続きを踏んで解決することが何より大切です。